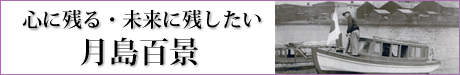羽子板に込めた親心
中国思想の影響で、「邪気を払う」という風習が日本にはたくさんありますね。
「冬至」(昼がもっとも短く、夜がもっとも長いとされる日)に、
無病息災を願って、南瓜(かぼちゃ)を食べたり、柚子湯に入って
邪気を払い、無病息災を願うといわれています。
*******
「邪気を払う」ものは、ほかにもあります。
お正月の和風の女児の遊び道具、
羽根つき遊びの羽子板が、邪気を跳ね(羽根)返す板として、
女子の健やかな成長を願う人気の縁起物でした。
羽根は、「無患子(むくろじ)」という木の実に羽根を付けたものです。
この名にも、子供が病気をしないようにという願いが込められています。
東京浅草寺境内の「羽子板市」は人気ですね。
華やかな羽子板に、我が子を思う親心がそっと込められていたのですね。
今では羽子板で遊ぶ女児の姿を見かけなくなりました・・・。
.
お歳暮を贈る
お歳暮を贈る習慣、続けていますか。
お歳暮を贈る時期は、12月に入ればいつ贈ってもよさそうです。
下旬になると、デパートのお歳暮売場もかなり混み合いますので、その辺は配慮して早目にすませたいものです。
どんなものを選ぶかは、相手の家庭に合ったものを心掛けたいですね。
これは義理で贈ったものだと感じさせるものは避けたいもの。
その家族構成に応じて、毎年変わったものを贈るにもよし。
また、いつも同じものを贈るのもよし。
今年はどんなお歳暮が我が家へ届くかと、相手の方のワクワクする気持ちと笑顔を想像しながら、
感謝の気持ちを込めて贈ってみてはいかがでしょうか。
和風月名〜霜月から師走へ
霜が降る月であるという11月「霜月」から、一年の終わりで皆が忙しく坊主も走り回るという12月「師走」へと、変わりました。
時が瞬く間に過ぎていくことを実感する昨今です。
先月は五穀豊穣の実りを祝う月でもありました。
11月23日は「勤労感謝の日」と、現代では呼ばれていますね。
もともとは、今年の稲の収穫を祝って、翌年の豊穣を祈願するお祭り日でした。
宮中や伊勢神宮などでは祭儀としてずっと執り行われています。
天皇が自ら今年実った稲を天神,地祇に感謝と恩恵を捧げる行事です。
『大言海』では11月を「食物(おしもの)月」といっています。
その略が「しもつき」に変わったということなのでしょう。
*******
12月「師走」の「師」は、『二中暦』では「法師」のことを意味しているそうです。
12月は僧を迎えて経を読ませるので師がはせ走る「師馳月(しはせづき)」、その略が「師走」というわけです。
12月の別名には、「春待月」「極月」「暮節」「暮歳」「晩秋」などがあります。
なるほどですね・・。
「たび寝よし 宿は師走の夕月夜」(松尾芭蕉)
江戸時代に生きた芭蕉が旅の宿で夕月を見ながら師走を味わったように、
現代人は、忙しい中にも、今年最後の月をたっぷりと、ゆったりと味わう時間を持ちたいものですね。
『下町の江戸散策ともんじゃツアー』
~楽しく歩き、心豊かに眺め、下町の味を楽しむ~
秋の雨の表現の仕方
「雨」を使った四季折々の表現はいろいろありますね。
「打ち水」のことを「作り雨(つくりあめ)」と呼ぶそうです。
茶の湯では、お客様をお迎えする前に、おもてなしとして玄関に打ち水をしますが、
それも「作り雨」という言葉を使えば更に奥深く感じられますね。
秋の雨は、「秋雨」「秋霖」「洗車雨」「御山洗」「秋時雨」などどいわれます。
錦秋の山に小雨が降り続く・・、そんな情景が目に浮かびますね。
月の見えない日に降る雨は、 「雨月」「雨夜の月」とも呼びます。
日本人の感性には、自然現象として雨を受け入れ、それを美的に表現するものがたくさんあります。現代人が忘れてしまった宝物がたくさんありますね。
明日の夜は、大和楽の代表作『河』を聴きながら、三味線や振りでの川の流れや雨の音などを見ていただこうと思っています。
西洋音楽とは違うものを感じていただけるはずです。
平成26年11月21日(金)午後7:00~9:00
~隅田川の江戸市井の暮らし~
場所:東京都中央区佃島コーシャタワー37階 なずな塾
※このイベントは終了しました
父との思い出〜童謡「里の秋」
私が秋になると思い出す歌、
それは父との思い出の童謡『里の秋』です。
静かな静かな 里の秋
お背戸に木の実の 落ちる夜は
ああ 母さんと ただ二人
栗の実煮てます 囲炉裏端
小学生の頃、郷里の家の二階でこの曲をオルガンで弾いていた時、
外の庭にいた父から、やめないでもっと弾いてくれと、言われたのを覚えています。
当時父は、宮城の気仙沼港を寄港として、主にマグロ漁業船の無線通信士をやって
いました。
父親(私から見れば祖父)が病弱で入退院を繰り返していたためにお金が必要だったのです。
.
.
あるときはアリューシャン列島まで、あるときは北海道までと、父は遠出をしていたので、
家に戻るのは年に、二、三回程度でした。
父が40歳の時、陸に上がりました。
その直前に乗らないかと誘いを受けた船に、気が進まず辞退したらしいのですが、
その船は洋上、転覆してしまったそうです。
父はそれを辞退したことで命拾いをしました。
.
.
まさに、「板子一枚 下地獄」の世界が海にはあります。
父が今も生きていられるのは、目に見えない人生の大きな選択をここでしたからでしょう。
*******
この童謡『里の秋』は、1945年に敗戦により失った領土からの引揚者の激励の
ためにNHKのラジオ番組で放送されたものだそうです。
私の父もこの曲を私にリクエストをしたのも、何か敗戦のころの思い出があったの
かもしれません。
明るい明るい 星の空
鳴き鳴き夜鴨の 渡る夜は
ああ 父さんの あの笑顔
栗の実食べては 思い出す
父がその後もしばらくの間 、海に出ていたので、
秋になると、この曲を思い出しては涙がこぼれたものです。
秋がやってくると思い出す『里の秋』です。
皆様も何か秋の思い出はありますか。
.
長月(ながつき)が終わり、神無月へ
9月の和風月名を書こうと思っていたら、もう昨日で9月も終わり。
9月は「長月(ながつき)」と呼ばれますね。
秋分のを過ぎると、昼より夜が長くなる月だから、秋の夜長の「夜長月」。
「稲刈月(いねかりつき)」から「い」と「り」が略されて、
「ねかづき」から「なかづき」を経て「ながつき」になったとか、
「稲熟月(いねあがりづき)」を略したのが「ながつき」だとか、説があります。
いずれにしても、稲がたわわに実る月ですね。
9月の中秋の十五夜、十六夜は美しかったですね。
10月は十三夜(旧暦9月13日)を楽しめます。
これは「後の月」とか「名残の月」とも呼ばれ、9月の十五夜月に劣らないほど
美しいとして愛でる日本独特の風習です。
秋の夜長は虫の音を楽しみ、新米、山や畑の恵みを楽しむいい季節ですね。
でも、食べ過ぎにはご用心。
人もこれまで蓄えてきたものの実りをゆっくりと楽しむ、
そんな季節でありたいですね。
.
曼珠沙華と秋分の日
今日は秋分の日。
お墓参りの日ですね。
秋分の日は、昼と夜の長さがほぼ同じで、これから夜が少しずつ長くなっていくのですね。
どことなくもの悲しさを感じます。
.
.
でも、秋の夜長を虫の音で楽しむ季節でもありますね。
今日は秋のお彼岸の中日でもあり、この日を中心にして、
仏教では彼岸会(ひがんえ)を行って、
それぞれのお寺では祖先の霊を慰める法要を行っていますね。
彼岸会の起源はかなり古くて、
延暦25年(805)の桓武天皇の時代に全国の国分寺で、
春秋2回の彼岸の7日間、金剛般若経読経をしたのが最初だそうです。
天界に咲くという曼珠沙華(彼岸花)が
何とも言えない雰囲気を漂わせていますね。
不思議な魅力のある花です。
===*===*===*===*===*===*===*===
10月にも行います。
ホームページをご覧くださいね。
“和のたしな美”講座
女性限定~和のマナー講座・基礎編~浴衣でアンチエインジング~
→ http://derivejapan.com/lessons/wano-manner/manner/
時の鼓動
いつの間にか季節は移ろい、自然は自由自在にその法則に乗って変化していきますね。
近くの公園のもみじが赤色に染まり始め、秋を大きく感じさせてくれます。
「もみじ」の名は、秋口の霜や時雨の冷たさに揉み出されるようにして色づく、
「揉み出るもの」の意味で、
「揉み出づ」が変化して「もみづ」となり、
その名詞形が「もみじ」となったそうです。
先日のスーパームーンは素晴らしかったですね。
こうして、いながらにして月をめでる喜びとともに、宇宙の運行の神秘なる営みを
感じます。
自然の営みは時空を超えて絶えず繰り返され、私たちはその瞬間、瞬間の
「時の鼓動」をともに味わう旅人です。
思いがけない自然災害が相次いでいますが、
人間の営為の中で地球そのものが悲鳴を上げているのはたしかだと思います。
人類はこの地球上で生かされていること、すべてに「ありがとう」の思いを
抱いて行動できたら、きっと地球も癒されるに違いありません。
ふた葉三葉ちりて日くるる紅葉かな (与謝蕪村)
蕪村のように、「時の鼓動」を味わい、時の移ろいとともに、
もみじの変わりゆく美しさを楽しむ心のゆとりとともに、
すべてを慈しむ心の寛さを持っていきたいものですね。
===*===*===*===*===*===*===*===
10月にも行います。
ホームページをご覧くださいね。
“和のたしな美”講座
女性限定~和のマナー講座・基礎編~浴衣でアンチエインジング~
→ http://derivejapan.com/lessons/wano-manner/manner/
お団子を食べる中秋の名月
十三夜は「栗名月」「豆名月」と、十五夜は「芋名月」とも呼ばれています。
実りの秋にふさわしい名前ですよね。
江戸の時代、庶民は、お月さまに、お団子、衣被(きぬかつぎ)という皮付きの
子芋、ゆでた栗、生柿、枝についたままの枝豆の五品を、
ススキとともにお供えしました。
十五夜の中秋の名月の日、朝早くから家族総出で団子づくりをすると縁起が良いと
いわれていました。
お供えのほかに、一人15個ずつ小さなお団子を食べるために準備しました。
十五夜の15という数に縁起を担いだのでしょうね〜。
自分のお団子を食べながら、お月さまを眺める特別な日だったのですね。
なんだか情緒があって、のんびりとしていて羨ましいです。
===*===*===*===*===*===*===*===
和のマナー講座~和のたしな美・中級編~
http://derivejapan.com/lessons/wano-manner/tashinami/
平成26年9月20日(土)、27日(土)14:30~16:30(土曜2回コース)
平成26年9月21日(日)、28日(日)14:30~16:30(日曜2回コース)
最高のお月さま
十五夜はあいにくの雨でしたが、昨夜の十六夜は美しかったですね。
秋の虫の音、涼風に揺れる秋の草花、夜露・・。
いい季節です。
日本人は月を愛でる繊細な感性を持っていますよね。
映画『利休にたずねよ』で、市川海老蔵扮する千利休が茶会で美しい黒い箱に水を
注いで満月をそこに映して見せた、あの感性には驚きました。
月の満ち欠けに細かく名前をつけて、
新月から数えて、十三日目を「十三夜月」、
満月の十五夜を待つ前日の十四日目は「待宵月(まつよいづき)」。
十五夜が過ぎると、月の出が遅れてくるということで、
月が出るのをためらっているから、いざようようだと、
「十六夜月(いざよいづき)」。
更に少しずつ月の出が遅れていくので、今か今かと立って月を待つ「立待月(たちまちづき)」。
更に次の日は座って待つから「居待月(いまちづき)」。
ついには寝て待つから「伏待月(ふしまちづき)」。
今のように街灯がない時代はお月様の明かりがたよりだったのですね。
生活に欠かすことのできない月光。
例えばベートーベンの『月光』とは、やはり日本人は抱く思いが違うように
思います。
===*===*===*===*===*===*===*===
和のマナー講座~和のたしな美~
http://derivejapan.com/lessons/wano-manner/tashinami/
平成26年9月20日(土)、27日(土)14:30~16:30(土曜2回コース)
平成26年9月21日(日)、28日(日)14:30~16:30(日曜2回コース)