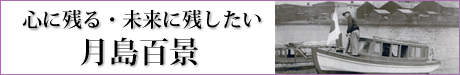源氏の信仰のみなもと八幡さま
源氏の信仰のみなもとは八幡大神〜in Kamakura〜
由比若宮(ゆいわかみや)
材木座の閑静な住宅街のなかにあって、探し当てるのに苦労するくらいの小さな神社です。住居表示は鎌倉市材木座1-7。
「元八幡」バス停の傍に石柱があるくらいなので、スマホの地図アプリで見つけるのがおすすめです。

バス停脇の石柱
この由比若宮(元八幡宮とも)については、鶴岡八幡宮の案内板にこのような記述があります。
「源頼義(よりよし)公が前九年の役(1051~1062)平定後、1063年報賽のため由比郷鶴岡の地に八幡大神を勧請したのに始まる。
1180年源頼朝公は源氏再興の旗を挙げ、父祖由縁の地鎌倉に入ると、まず由比郷の八幡宮を遥拝し「祖宗を崇めんが為」小林郷北山(現在地)に奉遷し、京に於ける内裏に相当する位置に据えて諸整備に努めた。」

由比若宮の入り口
源頼朝像
八幡大神とは、応神(おうじん)天皇(第15代)・神功(じんぐう)皇后(応神天皇の母)・比売(ひめ)神(アマテラスとスサノウとの誓いで生まれた女神で、
主神の母、妻、娘などとされる。応神天皇の皇后とする説あり。)の三柱の神が、あたかも一柱の神のように呼ばれたものですが、
なにか三位一体説みたいに見えますね。
神功皇后は、後の応神天皇を身ごもったまま三韓征伐を行ったとされる勇壮な話が有名ですが、それも影響があってか武神、弓矢の神とされるようになったようです。
武神であれば、源氏や平氏などの武士たちが尊崇するようになるのも無理からぬことで、特に清和源氏が氏神として祀ったことで、
宇佐八幡(九州大分)―石清水八幡(京都)―鶴岡八幡(鎌倉)と繋がっていき、ひいては日本全国に広がったとのこと。
日本は鎌倉、室町、江戸と武家の天下が長く続いたこともあり、日本一数の多い神社が八幡宮になったのですね。
源頼義が、海(由比ガ浜)をまじかに臨む風光明媚な地「由比郷鶴岡」に八幡宮を勧請し、それが後の鶴岡八幡宮・鎌倉幕府の隆盛に繋がっていくなんて、なにか歴史のロマンを感じられないでしょうか。

由比ガ浜西
由比ガ浜東
現在の由比若宮は、ほんとに小さなお社だけの神社として、悠久の歴史の中に佇んでいます。
由比若宮
お地蔵さまは6レンジャー
前回の円応寺から大分北鎌倉駅方向に戻ったところ、
長寿寺の脇から、亀ヶ谷(かめがやつ)坂切通しに入ることができます。
三方を山で囲まれた鎌倉とその外部とを結ぶ道は七つあり、
鎌倉七切通し(七口とも)と呼ばれていますが、
この亀ヶ谷坂切通しもその一つ。
円覚寺や建長寺のある山ノ内と寿福寺、英勝寺のある扇ガ谷を結ぶ経済的にも軍事的にも重要な切通しとして活躍しました。
1180年源頼朝が安房から大軍を引き連れて鎌倉入りしたときは、この切通しだけが北から入ることのできる唯一の道であったとのことで、由比ガ浜の元八幡(由比若宮)に向かったと伝えられています。

この亀ヶ谷坂の山ノ内側に六体のお地蔵さまがひっそりと祀られています。道に気を取られて歩いているときっと気が付かずに通り過ぎてしまいそうな、古びた六体のお地蔵さま・・・。
いわれも何も書かれてはいないのですが、通るたびに気になって手を合わせます。
鎌倉駅西口から御成小学校前を通り鎌倉文学館に向かう途中の交差点にも、六体のお地蔵さまが祀られています。
鎌倉時代、その近くに刑場があり、そこで処刑された罪人たちの霊を慰めるために建立されたものといわれます。
六体のお地蔵さまをお祀りするのは、死後に輪廻転生する世界(生きている間も六道輪廻をしているのですが)、
地獄・餓鬼・畜生・修羅・人閒・天の六道に合わせ、それぞれのお地蔵さまが苦しんでいる衆生を救ってくださるという信仰に基づくものです。
そうだとすると、亀ヶ谷坂の六地蔵は、新田義貞の鎌倉攻めの際この切通しでの戦いで亡くなった武士の霊を慰めるためのものなのかも(仮粧坂切通しの激戦が有名ですが)・・・・・。
そんなことを思いながら、昼なおほの暗い亀ヶ谷坂切通しを歩きました。
道端で見つけたミツマタ
笑っている?閻魔さま
北鎌倉駅から鎌倉街道を南東に鶴岡八幡宮方向にずっと歩いて行くと、
建長寺を過ぎて巨福路坂洞門の手前右側に円応寺があります。
閻魔大王座像(国重要文化財)で有名なお寺ですが、それほど観光客が多くはなく、割と静かにお参りができます。
鎌倉街道からの石段を上っていくと、狭い寺域の真正面に本堂があり、
うす暗い中に閻魔様がほの明るく見えています。
運慶作の「笑い閻魔」と呼ばれています。
運慶といえば、鎌倉時代に活躍した仏師です。写実的で勇壮な金剛力士像などが有名ですね。
この運慶ですが、閻魔大王座像にはこのような逸話が伝わっています。
運慶が頓死して閻魔様の前に引き出されたとき、
「お前は生前の罪により、地獄へ落ちるべきところであるが、もしお前がわしの姿を彫像し、その像を見た人々が悪行をなさず、善い縁に導かれるなら、お前を今一度娑婆に戻してやろう。」と言われ、
運慶がそれを約束したので息を吹き返したというのです。
運慶は生き返った喜びに思わず笑いながら閻魔像を彫ったため、閻魔様のお顔も笑っているように見える・・・と。
閻魔様をよくよく拝見したところ、
やっぱり怒っているように見えるのですが・・、
皆さんにはどのように見えますか?
鎌倉を静かに見守る太田道灌
太田道灌のお墓を見つけました。
道灌は扇谷(おおぎがやつ)上杉家の家宰(かさい)で、元々の江戸城を築いたことで有名ですが、鎌倉の源氏山から寿福寺に抜ける途中の下り坂の脇(英勝寺の墓地の裏側)にひっそりと佇んでいました。
傍らにある碑文を要約すると、
「徳川家康の側室のお勝の方が、出家後に英勝院と号し、三代将軍家光から源氏山一帯を賜って、英勝寺を開いた。この太田道灌の墓は、1826年水戸徳川家の子孫である英勝寺住職が再建したものである。」とのことでした。
あんなに有名な武将のお墓にしては、随分と質素で小振りなお墓でしたが、ここ以外でも伊勢原市に首塚、胴塚があるとのこと。
なお、道灌は刺客に殺されたということですが、刺客が読んだ上の句「かかる時さこそ命の惜しからめ」に、「かねてなき身と思い知らずば」と下の句を返したということです。
意味は、「このような時、どんなに命が惜しいだろう。」、「前もってこの身は無常であると悟っていなかったならば。」です。・・・すごい。
奇しくも辞世の句となった句が、今まさに刺客に刺された時に詠まれようとは。
泰然自若とした人としてのあり様に、感服するばかりです。