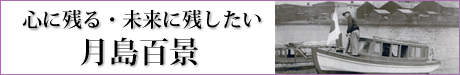【七十二候から】34 「桐始めて花を結ぶ」
【七十二候から】34
「桐始めて花を結ぶ」
皆様、おはようございます。
最も暑い真夏の頃「大暑」を迎えました。
.
桐の花が梢の高いところで紫の淡い色の花を咲かせるのがこの時期です。
古来から桐は鳳凰が宿る神聖な木として大事にされ、
「菊の御紋章」に次ぐ高貴な紋章として、
天皇家や武家で重んじられてきました。
.
500円玉を見てみてください。
表に描いてあるのが桐なのですよ。
.
娘が生まれたら桐の苗木を植え、
お嫁入りの時に伐採して嫁入り箪笥にするという習慣がありました。
大切な着物や衣類を保管してくれる大事な嫁入り道具ですね。
日本の暮らしの中で、桐は高貴な紋章として、
また身近な家具として(高価なものですが)息づいていますね。
.
.
現代の生活の中からは桐の木も花も遠のいてしまっているように思います。
.
詩人北原白秋は『桐の花』(1913年・大正2)という処女歌集を著します。
「桐の花とカステラの時季となった。」と、始まります。
文明開化の象徴であるカステラ。そして桐の花。
古いものと新しいものとが交錯しているように見えます。
恋い焦がれた女性への思いを綴った歌集『桐の花』。
恋心は「桐の花が咲くと冷たい吹笛(フルート)の哀音を思ひ出す」と、
こんな繊細な感性を心の奥から引き出したのですね。
ため息が出るようです・・。
.
.
どうぞお体にお気をつけてお過ごしくださいませ。
今日も佳き一日になりますように。
.
【七十二候から】33 「鷹乃学を習う(たかわざをならう)」
【七十二候から】33
「鷹乃学を習う(たかわざをならう)」
皆様、おはようございます。
鷹のひなが、飛び方を覚え、
巣立ちをし、自分で獲物を捕らえて、
一人前になっていく頃です。
都会暮らしでは、現代は鷹との生活なんてほど遠いものですね・・。
.
昔の武将はよく鷹狩りをしていましたよね。
時代劇でも時々見かけます。
.
.
東京の浜離宮恩賜公園は、
江戸時代に将軍家の御鷹場(おたかば)でした。
今でも伝統ある鷹狩の技「放鷹術(ほうようじゅつ)」の実演がお正月に行われています。
.
江戸時代の名残で、「鷹匠町」という地名も残っているところが多いのではないでしょうか。
.
.
モンゴルの女の子が鷹匠に育っていく場面をテレビで見たことがあります。
鷹と心を一つにして、ともに訓練していく姿は感動的でした。
鷹とのコミュニケーションを作り上げていくのは楽しいでしょうね。
鷹匠として女の子も成長し、鷹も共に成長していく喜び、
醍醐味でしょうね。
.
本日も素晴らしい一日をお過ごしになりますように。
.
【七十二候から】32 「蓮始めて開く(はすはじめてひらく)」
【七十二候から】32
「蓮始めて開く(はすはじめてひらく)」
皆様、おはようございます。
蓮の花が咲き始める頃です。
「蓮は泥より出でて泥に染まらず」
と言われますね。
.
二千年前の弥生時代の蓮の実が、現代に花を咲かせたなんて・・。
1951年、千葉の落合遺跡で発見された蓮の実です。
.
.
時を超え、土の中で気の遠くなるような歳月を過ごし、
生命力を蓄えていたとは、その神秘の力に驚嘆するばかりです。
.
泥の中で咲く蓮の花のように生きなさいと、
蓮の花を見る度に、メッセージを語りかけてくるように思います。
乗り越えられないものは与えられないのだと。
.
今日東京下町では、先祖の霊を迎える日。
おがらをたいて、盆提灯で迎え火をします。
今こうして日々つつがなく暮らせるのは、ご先祖さまのおかげ。
感謝の心を抱いて生きる人は素晴らしいですね。
.
【七十二候から】31 「温風至る(おんぷういたる)」
【七十二候から】31
「温風至る(おんぷういたる)」
皆様、おはようございます。
そろそろ梅雨が明け、夏の熱風が吹き始める頃。
梅雨が明けて、本格的に夏になる頃を「小暑」よ呼びます。
梅雨明けはいつ頃になるのでしょうか。
もうすぐですね。
梅雨明けの頃に吹く風を「白南風(しらはえ)」と呼ぶそうです。
.
白い南の風と書きますね。
白は雲の色。
.
「白南風」は、梅雨が明け、黒雲が去って空に巻雲や巻層雲が白くかかる頃、
そよ吹く爽やかな南からの季節風のことを、そう呼ぶのですね。
漁師さんたちが海へ出る目安としていました。
.
七夕の今日、星に願い事をしましょうか。
.
新暦ではちょうど梅雨の時期ですので、天の川が見えないことが多いですね。
織姫と彦星は、
雨のために天の川を渡れない時には、
それぞれカササギに乗って会いに行くといわれています。
天空を仰いで何も見えないとしても、
きっと二人は、今宵も一年に一度の逢瀬を楽しむことでしょう。
.
【七十二候から】30 「半夏生ず(はんげしょうず)」
【七十二候から】30
「半夏生ず(はんげしょうず)」
皆様、おはようございます。
「半夏(からすびしゃく)」が生え始める頃。
そろそろ田植えを終わらせる農事の節目とされました。
農家の人たちは忙しさが一段落し、
讃岐地方ではでは、田植えを手伝ってくれた人たちに労をねぎらう
うどんのふるまいをするという習わしがあったとか。
というわけで、明日は「うどんの日」でもあります。
.
.
私たちの住む日本は稲作の国。
美味しいお米をいただくためには
88もの手間がかかると、いわれていますよね。
大自然へ、作ってくださる方へ、お米へ、食べ物へ、
今日も感謝しながらいただきましょう。
ありがとうございます。
.
【七十二候から】29 菖蒲華さく(あやめはなさく)」
【七十二候から】29
菖蒲華さく(あやめはなさく)」
皆様、おはようございます。
「菖蒲華さく」頃。
あやめが咲いたら、梅雨が到来する。
そんな目安でもあったのですね。
.
あやめは初夏に咲く美しい紫の花です。
「いずれ あやめか かきつばた」といわれるように、
かきつばたや花しょうぶなどとも似ていますが、
あやめの花にある網目模様で見分けることができます。
ちょっと注意して見てみてくださいね。
.
.
.
吉原の風物詩を描いた清元『北州』は、
狂歌で知られる江戸の文化人、太田蜀山人の手になるものです。
「恐れ入谷の鬼子母神」
は、有名ですね。
.
清元『北州』では、
「鳴くや皐月のあやめ草
あやめも分かぬ単衣物」
と、夏の風物として「あやめ」を描いています。
初夏のホトトギスが鳴く頃、
着物は袷から単衣へ、
織の目もはっきり分からないような白黒の単衣物へと、
衣替えをしていく様子を掛け言葉で描写しています。
.
新緑広がる季節の爽快感と美しい女性を彷彿とさせますね。
.
.
もう直ぐ梅雨の季節ですね。
お体に気をつけてお過ごしくださいませ。
.
【七十二候から】28 「及東枯る(なつかれくさかれる)」
【七十二候から】28
「及東枯る(なつかれくさかれる)」
皆様、おはようございます。
「夏至(げし)」を迎えました。
一年で日が一番長く、夜は一番短い日。
とは言え、梅雨の最中。
夏至の時期は日照時間が冬至の頃よりも少ないと言われています。
雨の日や曇り空の日が多く、日照時間が少なく、「梅雨寒(つゆざむ)」と呼ばれる肌寒い日もあるからだそうです。
ヨーロッパでは「夏至祭」が行われますが、
日本では、田植えを終えて一息つく時期ですね。
.
.
「うつぼぐさ」ってご存知ですか。
田んぼのあぜ道や野原に咲いている雑草です。
「夏枯草(かこそう)」とも呼ばれています。
初夏に紫色の花を咲かせ、真夏になると花穂が茶色に変色するので、
まるで枯れたように見えるのです。
ちょうど「及東枯る(なつかれくさかれる)」頃なのですね。
これを田植えの目安にもしてきたのです。
.
.
「うつぼぐさ」は、
身近な薬草として暑気払いにお茶として飲まれてきたということです。
捻挫や腫れた時の塗り薬として、そしてうがい薬としても。
英語では、「all-heal(すべてを癒す)」のだそうです。
身近な雑草にこんな効用があったのですね。
今度見つけたら、じっくりと眺めてみたいです。
身も心も癒されるような薬草が、こんなにそばにあったなんて。
【七十二候から】27 「梅子黄なり(うめのみ きなり)」
【七十二候から】27
「梅子黄なり(うめのみ きなり)」
皆様、おはようございます。
梅の実が熟して色づく頃ですね。
あちこちで梅雨入り宣言が出されました。
なんと、沖縄ではもう梅雨が明けたというニュースが流れましたけど・・。
梅雨の訪れとともに、梅の実も熟し始めますね。
木から落ちた熟した梅の実は芳醇な香りがします。
梅干しを漬けるのを毎年楽しみにされている方も多いことでしょう。
ご自宅のお庭の梅で毎年梅を楽しめることができたら、最高ですね。
工夫次第でビネガー漬け、シロップ漬け、また梅酒や梅ジャムもいいですね。
大自然は豊かさを私たちに与えてくれます。
当たり前のように目で見て、耳で聞いている
「梅雨(つゆ・ばいう)」という言葉ですが、
「梅」の字が入っています。
菅原道眞が愛した梅の花を初春に愛で、初夏には実を楽しむ。
昔から日本人にとって、梅の木は大切なものだったのですね。
今日も幸せいっぱいの一日となりますように。
【七十二候から】26 「腐草蛍と為る」
【七十二候から】26
「腐草蛍と為る(ふそうほたるとなる)」
皆様、おはようございます。
ちょうどこの時期は、蛍を楽しむ季節ですね。
「蛍狩り」という言葉も風情がありますね。
浴衣に団扇を手に持ち、足元には下駄。
多くの舞踊でも、夏の風物詩としてこの風情を表現しています。
.
.
腐った草が蛍に生まれ変わると、昔の人は信じたそうです。
死から生が生まれ、生が死を迎える、
そのサイクルの中で人も生かされていることを
生活の中で自然に感じていたのでしょう。
.
.
子供の頃は、近くにたくさん蛍がいたのに、もうほとんど見かけなくなってしまいました。
夜になると、吊るした蚊帳の中に蛍を入れて、
ぼんやり灯る明かりを夢見心地で楽しんだりもしたものです・・・。
現代の東京では椿山荘の「ほたるの夕べ」が有名ですね。
ただ見に行って、そのまま帰ってくるもよし、
食事をするもよし。
たまにはちょっと贅沢に食事を楽しみながら、
幻想的な蛍の明かりをただただじっと眺めていたいものです。
夢かうつつか、うつつが夢か。
今を生きることに重ね合わせながら・・・。
【七十二候から】25 「蟷螂(かまきり)生ず」
【七十二候から】25
「蟷螂(かまきり)生ず」
皆様、おはようございます。
昨日は「芒種(ぼうしゅ)」、そして「蟷螂生ず 」日。
二十四節気の一つ「芒種」は、稲や麦など穂の出る植物の種を蒔く頃です。
稲の穂先にある針のような突起を「芒(のぎ)」というところからきています。
ちょうど季節はカマキリが生まれ出る頃。
カマキリは、育ち始めた稲や野菜の葉に手をつけずに、
害虫を捕まえてくれます。
人にとっては、田畑のヒーローです。
自然とはうまくしたものですね。
ちゃんバランスをとってくれています。
.
.
京都の祇園祭では、
からくり仕掛けのカマキリを 乗せた「蟷螂山(とうろうやま)」、
別名「かまきり山」という山車があるそうですね。
祇園祭でカマキリは、神の能力を持つもの、神の使者として崇められています。
.
.

カマキリがカマを振り上げて強いものに立ち向かう勇壮な姿は武勇伝にもなぞらえています。
南北朝時代の足利義詮と戦って死んだ四条隆資家では、
後に御所車にカマキリを乗せて巡行したということです。
これが 祇園祭の山車「蟷螂山(とうろうやま)」の始まりです。
.
.
元々は、中国の春秋時代の故事「蟷螂の斧(とうろうのおの)」に由来しています。
斉の荘公が乗る馬車の前にカマキリが現れ、カマを振り上げて立ち向かってきたというのです。
荘公はその雄々しい姿に感動し、馬車でカマキリを踏まないように、
馬車を翻し違う道を通ったということです。
弱き者でも我が身を挺して全力で挑む姿に心打たれたのでしょう。
.
.
皆様、今週もすべては完璧、大成就でありますように。
健やかにお過ごしくださいませ。